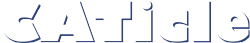地球温暖化、異常気象により年々平均気温が高くなる中、夏の暑さは人だけでなく、愛猫にとっても大きな負担になります。猫は体を覆う毛があるため暑さに強そうに見えますが、実は人間よりも暑さに弱い部分があり、熱中症などの危険が潜んでいます。この記事では、「なぜ猫は暑さに弱いのか」「どんな症状が出るのか」「日常でどんな対策ができるのか」「市販の暑さ対策グッズの使い方」などを、専門用語をできるだけわかりやすく解説しながらお伝えします。
最後まで読んでいただき、猫ちゃんと一緒に暑い季節を乗り越えましょう!
猫の体温調節の仕組みと暑さの限界

猫はなぜ汗をかかないのか?
人間には全身にエクリン腺という汗腺が分布しており、汗を蒸発させることで体温を下げます。一方、猫のエクリン腺は肉球のみに存在し、その発汗量はごくわずか。体全体の温度を下げる役割は果たせません。
猫の主な放熱方法
猫は汗ではなく、次のような方法で体温を下げます。
パンティング(口呼吸)
犬のように口を開けてハアハアと呼吸し、呼気から熱を放出します。ただし猫は犬よりもこの方法が苦手で、パンティングが見られる時点でかなり危険な状態と考えてください。
耳や肉球からの熱放散
耳や肉球は血管が多く集まっており、血流を増やして熱を外に逃がします。暑い日に猫の耳が赤くなっているのは、体温を下げようとしているサインです。
毛づくろいによる気化熱
舌で被毛を舐め、唾液が蒸発するときに体温を奪います。これも猫独自の涼み方ですが、限界があります。
猫が暑さに弱い理由

高湿度が放熱を妨げる
日本の夏のように湿度が高いと、汗や唾液が蒸発しづらく、猫の放熱効率が著しく低下します。そのため、湿度管理は温度管理と同じくらい重要です。
毛皮構造の影響
猫の被毛は二層構造(アンダーコートとトップコート)で、冬は保温に優れますが、夏は熱がこもりやすい構造にもなります。特に長毛種は空気の流れが悪く、熱がこもる傾向が強いです。
熱中症の危険性と症状

猫の熱中症とは
熱中症は、体温が急上昇し、体の冷却機能が追いつかなくなる状態を指します。猫の場合、体温が40℃以上になると命に関わる危険な状態に入ります。
主な症状
- 急激な呼吸の速まり(パンティング)
- よだれが増える
- 歩行がふらつく
- 意識がもうろうとする
- 嘔吐や下痢
- ぐったりして動かない
海外の調査データによると、猫の熱中症は発症から数時間以内に適切な処置を行わなければ致死率が50%以上に達します。猫ちゃんの様子が怪しいと思ったら、まずは獣医師さんに相談しましょう。
猫の暑さ対策の基本

室内温度と湿度の管理
猫が快適に過ごせる環境は、一般的に温度25〜28℃、湿度50〜60%が目安とされます。
特に湿度は見落とされがちですが、高湿度は猫の放熱効率を大きく低下させるため要注意です。
対策例
・エアコンは除湿モードを活用
・サーキュレーターで空気を循環
・窓の遮光カーテンで直射日光を防ぐ
水分補給を促す工夫
猫はあまり水を飲まない習性があるため、夏は意識的に水分摂取を促す必要があります。
工夫例
・複数の場所に水皿を置く
・冷たすぎない常温水を用意
・流れる水が好きな猫にはペットファウンテンを設置
・ウェットフードやスープ状のごはんで水分を補給
海外の研究では、水の場所を3カ所以上に増やすと飲水量が約30%増加することが報告されています。
具体的な暑さ対策アイデア

市販の冷却グッズの活用
市販の暑さ対策グッズは、すぐに導入できて効果も高いのが魅力です。猫の体質や好みに合わせて選びましょう。
代表的なグッズと特徴
冷却ジェルマット
・中に冷却ジェルが入っており、体を乗せるとひんやりします。
・電気不要で安全性が高いですが、かじる癖がある猫には不向き。
アルミ製クールプレート
・アルミは熱伝導率が高く、体温を効率的に逃がします。
・硬い感触が苦手な猫もいるため、置き場所に工夫が必要。
ペット用冷風扇
・水や氷を入れることで、冷たい風を送り出します。
・直接体に当てず、空気を循環させるように使うのがコツ。
注意点:
海外のペット安全協会の調査によると、猫の約15%が新しい冷却グッズを警戒して使わないことがあるため、慣らし期間を設けることが重要です。
在宅時と不在時の温度管理
飼い主が家にいるときと、外出しているときでは、温度管理の方法を変える必要があります。
在宅時のポイント
・エアコンをこまめに調整
・猫の様子を直接観察しながら扇風機や冷却マットを併用
・室内の直射日光を遮る(カーテンやすだれ)
不在時のポイント
・室温が高くなる時はエアコンはつけっぱなしにする
・エアコン使用時は窓を完全に閉めて冷気を逃がさない
・万が一の停電対策として保冷剤や冷却マットを複数設置
・エアコンを使用しない時は熱がこもらないよう換気対策をする
アメリカの米国動物虐待防止協会では、「外出時でも必ずエアコンを稼働させること」を推奨しています。猫は犬のようにパンティングで体温を下げる能力が低いため、閉め切った室内は短時間で危険な温度になります。
ケージやキャリーケース内での対策
夏場に動物病院や移動のためキャリーケースを使うと、内部が高温になりやすく危険です。
対策例
・保冷剤をタオルで包んでキャリーの片隅に設置
・通気性の良いキャリーを選ぶ(メッシュ部分が多いもの)
・車内で待機する場合は必ずエアコンをつける
ドイツの獣医協会の実験では、夏の炎天下では停車中の車内温度がわずか10分で40℃を超えることが確認されています。これは猫にとって致命的な温度です。
猫の年齢や体質別の暑さ対策

猫は年齢や体質によって暑さへの耐性が大きく異なります。これは、人間でいうところの「子どもや高齢者が熱中症になりやすい」のと同じ理由です。体温調節の能力や体力が異なるため、それぞれに合った対策が必要です。
子猫の暑さ対策
子猫(生後6か月未満)は、体温を自分で安定させる機能がまだ十分に発達していません。
そのため、真夏はもちろん、室温が急に高くなるだけでも危険です。
具体的な対策
室温を一定に保つ
エアコンで27℃前後をキープ。
温度計と湿度計を併用し、湿度は50〜60%に。
冷却と保温の両方を準備
冷却マットを設置する一方で、寒く感じたときに入れる毛布やタオルも用意。
飲水の工夫
子猫用の浅い水皿を複数設置。
水分補給が苦手ならウェットフードを増やす。
ポイント:
海外の研究では、子猫は成猫に比べ水分不足による体温上昇リスクが約2倍高いとされています。
高齢猫の暑さ対策
高齢猫(10歳以上)は、代謝や循環機能が衰え、暑さに対する反応が遅くなります。
さらに腎臓病や心疾患を抱えていることが多く、熱中症が重症化しやすい傾向があります。
具体的な対策
直射日光を避ける環境
・窓際にはUVカットカーテンを使用。
・冷却マットやアルミ板を日陰に設置。
こまめな水分補給
・自動給水器で新鮮な水を常に提供。
・スープタイプの猫用おやつで水分補強。
短時間でも温度差に注意
・エアコンを切った後の急な室温上昇が危険。
・夏場は外出時もエアコンをつけっぱなしにする。
参考:
日本の農林水産省によるペット熱中症調査では、高齢猫は熱中症発症率が成猫の約1.7倍という結果が出ています。
持病のある猫(腎臓病・心疾患など)
腎臓病や心疾患を持つ猫は、体内の水分や血流のバランスを保つ能力が低く、暑さに弱いです。特に腎臓病の猫は脱水が病状を悪化させます。
具体的な対策
・獣医師と相談し、夏場は水分摂取量を増やす計画を立てる
・尿量や食欲の変化を毎日記録
・体重減少や元気の低下があればすぐに診察
参考:
海外の調査では、慢性腎不全の猫は体温が39℃を超えると症状が急激に悪化すると報告しています。
長毛種と短毛種の違い
毛の長さや密度も暑さの感じ方に大きく影響します。
長毛種(ペルシャ、ラグドールなど)
・毛が密集しているため熱がこもりやすい。
・定期的なブラッシングで毛の通気性を確保。
・夏はサマーカット(部分的なトリミング)も有効だが、皮膚保護のため全剃りは避ける。
⇒ 参考:ペルシャ
短毛種(アメリカンショートヘアなど)
・長毛種ほどではないが、黒系の毛色は熱を吸収しやすい。
・日向ぼっこ中の体温上昇に注意。
⇒参考:アメリカンショートヘア
肥満猫への特別ケア
肥満は体温調節機能を鈍らせます。脂肪が断熱材のように働き、体の熱を逃がしにくくなるからです。
対策例
・夏場は高カロリーなおやつを減らし、運動は朝晩の涼しい時間帯に。
・冷却マットを複数の場所に配置し、移動しながら体温を下げられる環境を作る。
・ダイエット中でも栄養不足にならないよう、獣医師の指導を受ける。
参考:
海外の調査では、肥満猫は正常体重の猫に比べ熱中症の発症リスクが3倍と報告されています。
飼い主が知っておくべき熱中症の初期症状と応急処置

猫の熱中症は、症状の進行が非常に早く、「少しおかしいかな?」と思ってから数時間以内に命の危険にさらされることもあります。特に初期症状は犬よりも目立ちにくく、見逃されやすいため、日頃から観察のポイントを知っておくことが重要です。
見逃しやすい初期症状
猫の熱中症は、必ずしも「ぐったりして動けない」という重症状態から始まるわけではありません。初期段階では、次のような小さな変化が現れます。
呼吸が浅く速くなる
個体差はありますが、猫は普段の安静時には1分間に20〜30回程度の呼吸をします。
暑さで体温が上がると、体を冷やそうとして呼吸回数が増えます。
犬のように舌を出してハッハッとする(パンティング)ことは少ないですが、口を半開きにして小さく息をする様子が見られることもあります。
落ち着きがなくなる、あるいは逆に無気力になる
・部屋の中をウロウロ歩き回って涼しい場所を探す
・急に動かなくなり、じっとして呼吸を整えようとする
こうした行動の変化は、飼い主が「いつもと違う」と気づくきっかけになります。
舌や歯茎の色がいつもより赤い
熱中症になると血流が増え、舌や歯茎の色が鮮やかな赤色になります。
普段の健康なときの色を知っておくと、変化に気づきやすくなります。
食欲の低下と水分摂取量の急増
突然フードを残す、水ばかり飲むようになる場合は注意が必要です。
特にシニア猫では、これらの変化が熱中症だけでなく腎臓病や心臓病とも関わることがあるため、早めの対応が必要です。
自宅でできる応急処置
初期症状が見られた場合、迷わず涼しい環境に移動させ、体温を下げることが最優先です。以下は応急処置の流れです。
涼しい場所に移動
エアコンが効いている部屋や、直射日光の当たらない風通しの良い部屋に移します。
エアコンは設定温度26〜28℃、湿度50〜60%程度が理想です。
冷却
・濡れたタオルで首の後ろ(頸動脈付近)、脇の下、内股をやさしく冷やす
・保冷剤をタオルにくるみ、猫の体に軽く当てる(直接肌には当てない)
※急激に冷やすと血管が収縮して体温が下がりにくくなるため、冷却は「じんわり」が基本です。
水分補給
猫が自分で水を飲める場合は新鮮な水を与えます。飲まない場合は無理に口に入れず、シリンジ(注射器型の給水器)で少量ずつ口の端から垂らすようにします。
※意識がはっきりしない場合は水を飲ませると誤嚥の危険があるため、絶対に与えないでください。
動物病院での治療例
熱中症が疑われたら、応急処置をしながら速やかに動物病院へ向かうことが重要です。動物病院での治療は以下のような流れになります。
体温測定と状態確認
直腸温を測り、重症度を判断します。猫の平熱は約38℃ですが、熱中症では40℃以上になることもあります。
酸素吸入
呼吸が浅く酸素不足になっている場合、酸素室や酸素マスクを使います。
静脈点滴
脱水や循環不全を改善するため、点滴で水分と電解質を補給します。
薬物療法
ショック症状や脳浮腫のリスクがある場合は、ステロイドや抗炎症薬が投与されることもあります。
入院管理
重症例では体温と血液データをモニタリングしながら数日間入院します。
猫の暑さ対策に役立つグッズ活用法

夏場の室温管理や水分補給は、飼い主の努力だけでは限界があります。
そこで活躍するのが、市販の暑さ対策グッズです。
ただし、猫は犬と比べて新しい物に警戒心を持つため、導入にはちょっとした工夫が必要です。
冷感マット・アルミプレート
仕組みと効果
アルミや冷感ジェルを使ったマットは、体温を吸収して逃がすことで猫の体を涼しく保ちます。
エアコンの効きにくい場所や、猫が好んで寝る日なたの近くに置くと効果的です。
選び方のポイント
体の大きさに合ったサイズを選び、表面が爪で傷つきにくいタイプが安心。
ジェルタイプは万一破れたときに中身を誤飲しないよう、ペット用に設計された安全素材のものを選びましょう。
慣らし方のコツ
最初はお気に入りの毛布やタオルを上に少し掛けて、においや感触に慣れさせます。
冷却首輪・保冷ベスト
仕組みと効果
首元や胸元に保冷剤を入れ、血流の多い部分を冷やすことで全身を効率的にクールダウン。
熱中症予防だけでなく、外出時(動物病院への移動など)にも有効です。
注意点
猫が動きを嫌がる場合は無理につけず、短時間から慣らすこと。
保冷剤は必ずペット用を使い、直接肌に触れないようタオルやカバーで包みます。
循環式自動給水器
仕組みと効果
猫は流れる水を好む習性があり、循環式給水器は常に新鮮で冷たい水を提供できます。
水分摂取量を増やすことで、体温調整だけでなく腎臓病の予防にもつながります。
選び方のポイント
フィルター交換が簡単なタイプ、静音設計のものがおすすめ。
夏場は特に、毎日フィルターと水を清潔に保つことが重要です。
クールハウス・遮熱カーテン
仕組みと効果
アルミ製や断熱素材で作られた猫用ハウスは、外気温の影響を受けにくく、ひんやり空間を提供します。
また、窓に遮熱カーテンやフィルムを貼ることで、室温の上昇を抑えられます。
導入のコツ
猫が普段から落ち着ける場所に設置すると、自然に使ってくれるようになります。
おもちゃを活用した暑さ軽減
仕組みと効果
暑い日中に激しい運動をさせると体温が上がって危険ですが、早朝や涼しい時間帯に軽く遊ぶことでストレスを発散できます。
特に水遊びおもちゃ(浮かぶボールなど)を使うと、水に触れることで涼しさも感じられます。
注意点
水嫌いな猫も多いため、無理に遊ばせず、興味を示した場合のみ短時間から試すのがベストです。
ポイント
猫はグッズを導入してもすぐには使わない場合が多いです。
そのため、「お気に入りのにおいをつける」「おやつを置く」「徐々に慣らす」など、心理的な配慮も忘れずに行いましょう。
熱中症になった場合の応急処置

猫は人間よりも暑さに弱く、重度の熱中症になると短時間で命に関わる危険があります。
まずは初期症状を見逃さないこと、そして迅速な応急処置と動物病院への搬送が重要です。
熱中症のサイン
- 呼吸が荒く、口を開けてハァハァと喘ぐ(パンティング)
- よだれが増える
- 舌や歯茎の色が赤くなる
- ぐったりして動かない
- 嘔吐や下痢
- 意識がもうろうとしている
※これらの症状が出たら要注意です。
応急処置の手順
1.涼しい場所へ移動
エアコンの効いた室内や日陰へ移動させ、風を当てて体温を下げます。
2.体を冷やす
濡らしたタオルや保冷剤をタオルで包み、首・脇・内ももなど大きな血管が通る部分に当てます。
氷水に直接入れるのは急激な冷却で危険なため避けましょう。
3.水を与える
自力で飲める場合は常温の水を少しずつ与えます。
無理に飲ませると誤嚥の危険があるため注意。
4.速やかに動物病院へ
応急処置で落ち着いても、内臓ダメージや後遺症が残る可能性があるため必ず受診します。
やってはいけないこと
- 氷水を直接かける(血管が収縮し、体温低下を妨げる恐れあり)
- 無理やり口に水を流し込む(誤嚥の危険)
- 症状が軽いと自己判断して放置する
ポイント
熱中症は「予防」が最優先ですが、万が一のときに備えて応急処置の流れを家族全員で共有しておくと安心です。
まとめ 〜愛猫を守るためにできること〜

夏場の猫の健康を守るためには、環境管理・水分補給・生活習慣の工夫が欠かせません。
さらに、グッズを活用することで快適な空間を作り、熱中症のリスクを大幅に減らせます。
飼い主ができる基本の5カ条
1.室温は25〜28℃、湿度は50〜60%を保つ
2.水は複数箇所に置き、飲みやすくする
3.遊びや運動は涼しい時間帯に行う
4.定期的なブラッシングで熱を逃がす
5.熱中症のサインと応急処置を覚えておく
猫は自分で「涼しい場所を探す」ことはできますが、環境そのものを整えるのは飼い主の役割です。
暑い季節も快適に過ごせるよう、日々の習慣と環境を見直して、大切な家族を守りましょう。