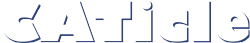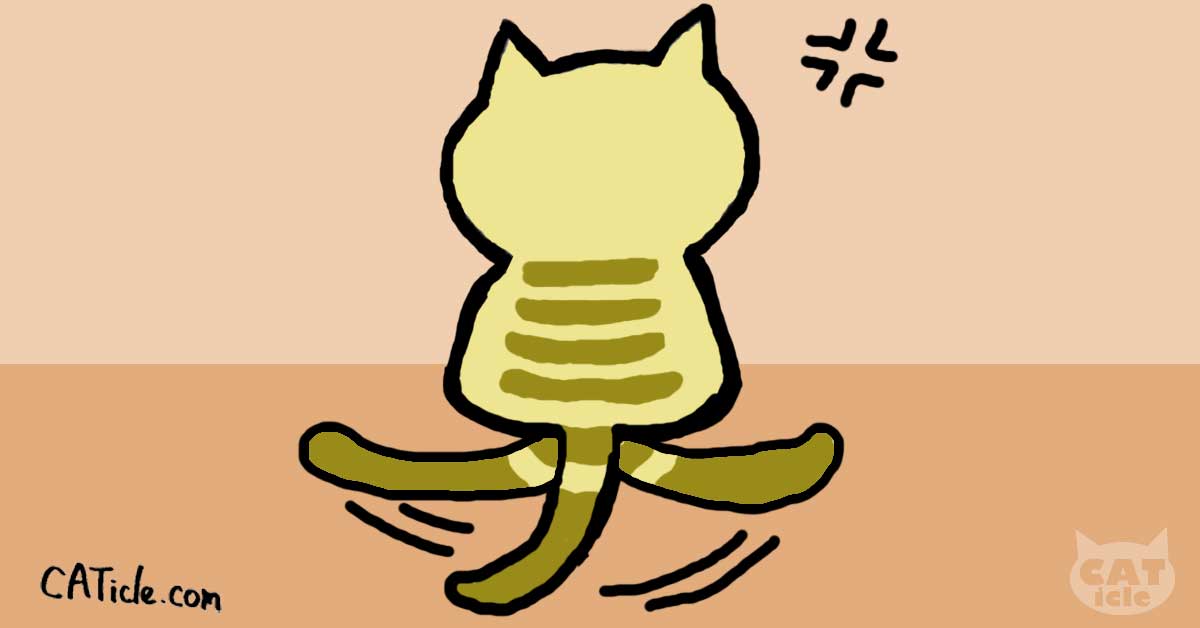猫と暮らしていると、「今この子はどんな気持ちなんだろう?」と思う瞬間がたくさんあります。ごはんのときにスリスリしてきたり、突然かみついてきたり、眠るときに一緒に布団へ入ってきたり。猫は言葉を話せませんが、体や目線、声を使ってしっかり気持ちを伝えています。
でも、猫のサインを「人間の感覚」でそのまま理解しようとすると、勘違いしてしまうこともあります。たとえば、
- ゴロゴロ鳴く=全部うれしいときだけ?
- 尻尾をブンブン振る=喜んでるの?怒ってるの?
- 見つめてくる=ケンカを売ってるの?甘えてるの?
こうした「なぜ?」を一つずつ解き明かして、「信頼のサイン」に注目して、わかりやすくまとめました。
具体例なども入れていますので、最後まで読んでいただくと、改めて猫ちゃんの行動に気づきがあるかもしれません。
猫が見せる「安心と信頼」の行動

目を細めて「まばたき」をする
猫は目をじっと見つめ合うことがあまり好きではありません。猫同士の世界では、長く目を合わせるのは「威嚇」や「警戒」を意味します。
けれども、信頼している相手には「ゆっくりまばたき」を見せてくれます。これは「リラックスしているよ」「安心しているよ」というサインです。人間でいうと、にっこり笑ってうなずくようなものです。
この「ゆっくりまばたき」は「猫のキス」と呼ばれることもあります。もし猫がやってくれたら、飼い主さんも同じようにまばたきを返してあげましょう
お腹を見せてゴロンと転がる
猫がお腹を見せるのは「無防備になっても安心」という証拠。野生ではお腹は急所なので、簡単に見せることはありません。
ただし、「お腹をなでていいよ」という意味ではないこともあります。触ろうとするとガブッとかまれるのは、「そこはちょっとやめて!」という意思表示。
例えば、お腹を見せてゴロゴロ転がる猫ちゃんに手を伸ばすとすぐに抱え込んでケリケリ攻撃したりすることもあるようです。それでもリラックスのサインなのは間違いありません
体をスリスリとこすりつけてくる
猫が人や家具に体をスリスリするのは、単なる「甘え」だけでなく「自分のにおいをつける」行動でもあります。猫の頬や体には「フェロモン腺」があり、そこから分泌される匂いをつけることで「ここは自分の安心できる場所」と確認しているのです。
猫は縄張りを大事にする動物なので、飼い主さんにスリスリするのは「あなたも仲間だよ」という印なのです。
しっぽを立てて近づいてくる
猫がしっぽをピンと立てて寄ってくるのは、喜びや親しみを表しています。
特に子猫が母猫に近づくときも同じようにしっぽを立てるので、「甘えたい」という気持ちの現れでもあります。
人間の行動に置き換えると、友達に手を振りながら近づいてくるようなイメージに近いかもしれません。
猫が少し不機嫌なときに見せる行動

猫はとても感情が豊かな動物です。人間のように「言葉」で怒ったり不満を言ったりはできませんが、しっかりと体やしっぽ、鳴き声で「いま機嫌悪いよ!」と伝えてきます。ここを見逃さないことが、猫との信頼関係を深めるポイントです。
しっぽをバシバシ振る
猫がしっぽを左右に大きく振るのは「イライラしている」「集中している」サインです。
たとえば、
- なでられるのに飽きたとき
- 他の猫や音に警戒しているとき
- 遊びの途中で興奮しすぎているとき
などに見られます。
人間でいうと、授業中にペンをトントン机に叩くようなものです。「落ち着かない」「ちょっとイラついてる」ときのしぐさになります。
耳が横や後ろに倒れる
猫の耳は感情のバロメーターです。
- ピンと前に向いている → 興味津々
- 横に広がる(イカ耳) → 警戒、不快
- 後ろに寝かせる → 怒り、恐怖
特に「イカ耳」は要注意。小さな物音や来客などで「落ち着けない」と思っていることが多いです。
猫の耳の動きはとても素早く、1秒で何度も耳の方向を変えることができます。人間の顔の表情と同じくらい、猫にとって耳は「感情を伝える道具」なのです。
突然の猫パンチや甘噛み
猫が遊んでいるとき、急に「パシッ」と手を出してきたり、カプッと噛んでくることがあります。これは必ずしも「本気で怒っている」わけではなく、「もうやめてほしい」や「遊びがヒートアップした」サインです。
人間でいえば、友達とじゃれあっているときに「ちょっと強すぎ!」と軽く止めるような感じです。
ごはんを食べない・隠れる
猫はストレスや不安があると、「食欲が落ちる」「姿を隠す」という行動をとります。
とくに環境が変わったとき(引っ越しや来客、模様替えなど)は注意が必要です。
猫は「変化」を嫌う動物なので、人間にとっては小さな変化でも、猫にとっては大事件に感じられることがあります。
人間でいうと、新しいクラスに入った初日、緊張してお弁当が喉を通らない…という感覚に近いかもしれません。
猫の「不機嫌サイン」は、決して「嫌い」や「もう一緒にいたくない」という意味ではありません。むしろ「これ以上はやめてほしい」というメッセージを正しく理解してあげれば、猫との関係はもっと良くなります。
猫が甘えたいときに見せる行動

猫は「ツンデレ」と言われることが多い動物です。普段はクールに見えても、実はとても甘えん坊なのです。甘えたいときにはわかりやすい行動を見せてくれます。ここを理解できれば、猫との暮らしはもっと楽しくなります。
スリスリしてくる
猫が飼い主の足や手に体をこすりつけるのは「甘えている」サインのひとつです。
実はこれは、単なるスキンシップだけでなく「自分のにおいをつける」意味もあります。猫の顔まわりには「臭腺」というにおいを出す器官があり、そこをすりつけることで「ここは私の大切な仲間」とマーキングしているのです。
帰宅すると猫ちゃんが玄関で「スリスリ」してくることがあります。これは「おかえり!寂しかったよ」と言ってのかもしれません。
ふみふみする
猫が前足で毛布やクッションを「ふみふみ」する姿はとても愛らしいものです。これは子猫のころ母猫のおっぱいを飲むときのしぐさが大人になっても残っているものです。「安心している」「甘えている」サインです。
ふみふみのとき、猫はゴロゴロと喉を鳴らすことが多いです。これもリラックスしている証拠です。人間でいうと、安心すると自然に鼻歌が出てしまうようなものかもしれません。
一緒に寝たがる
猫が布団やベッドに入ってきて一緒に寝ようとするのは、最大級の信頼行動です。夜は猫にとっても警戒心が強まる時間。そのときに「一緒にいれば安心」と思ってくれているのです。
猫は人の体温を好みます。特にお腹や胸の上はあたたかく、鼓動のリズムが子猫時代を思い出させて安心感を与えるようです。
鳴き声で呼ぶ
猫が「にゃー」「みゃー」と鳴いて飼い主を呼ぶことがあります。これは「かまって」「遊んで」「ごはんちょうだい」など、さまざまな意味があります。
野生の猫同士はあまり鳴きません。人に飼われるようになってから、猫は「鳴いて気持ちを伝える」ように進化したと考えられています。
猫が甘えるときの行動は、どれも「安心している」「大好き」という気持ちの表れです。スリスリ、ふみふみ、一緒に寝る…。どの行動も、飼い主にとっては大きなご褒美ですね。
猫が警戒しているときに見せる行動

猫は甘える一方で、とても警戒心の強い生き物です。知らない音や人、急な動きに敏感に反応します。そんなとき猫は「怖いから近づかないで!」というサインを体全体で出します。飼い主がこれを見分けられると、トラブルを未然に防ぐことができます。
毛を逆立てる
猫が怒ったとき、背中やしっぽの毛が逆立つことがあります。これは「威嚇(いかく)」のポーズです。自分の体を大きく見せて、敵を追い払おうとしているのです。
しっぽが「ボワッ」と大きくなるのも同じ理由です。まるでフワフワのマフラーのように膨らんで見えます。人間でいうと、怖いときに無意識に背筋を伸ばしたり、胸を張ったりして強く見せようとするのに似ています。
低い声で「ウーッ」とうなる
猫が「ウーッ」と低くうなるのは、本気で警戒しているサインです。このときに無理に近づいたり触ったりすると、猫パンチや噛みつきが出る可能性があります。
野生時代の猫は「低い声」で威嚇することで、相手に「本気で危険だ」と伝えていました。
耳を寝かせる(イカ耳)
耳を横にぺたんと倒す「イカ耳」は、不安や警戒のサインです。耳を横にすることで、音の方向を探ったり、できるだけ頭を小さくして攻撃を避けようとしています。
人間でいえば「身をすくめて、なるべく攻撃を受けないように守る姿勢」と同じです。
背中を丸めて体を小さくする
猫が背中を丸めて体を縮めるときは「怖いけれど攻撃したくない」という気持ちの表れです。逆に、毛を逆立てて背中を高くそらすときは「戦うぞ!」という意思表示。背中の丸め方にも違いがあります。
雷が鳴ったとき、押し入れに隠れて背中を丸める猫もいます。これは「できるだけ小さくなって気配を消そう」という防御反応です。
背中を丸めて小さくなるのは、弱い立場を相手に見せて「攻撃しないで」と伝えているとも言われます。
しっぽの動き
猫のしっぽは感情のアンテナ。警戒しているときは大きくバタバタ動かしたり、しっぽの先だけをピクピク震わせたりします。猫がソファの上でしっぽをパタパタさせているときは「今は構わないで!」のサインを出している場合もあります。
猫が警戒しているときは、毛を逆立てる、低くうなる、耳を寝かせるなど、わかりやすいサインを出します。飼い主はそれを正しく読み取り、「今はそっとしておこう」と距離をとることが大切です。猫の気持ちを理解できれば、お互いに安心して暮らせます。
猫がリラックスしているときの行動

猫は警戒心の強い動物ですが、安心できる環境ではとてもリラックスした姿を見せてくれます。猫の「くつろぎサイン」を理解できると、「この子は今とても幸せなんだな」と実感でき、飼い主にとっても安心材料になります。
ゴロゴロとのどを鳴らす
猫がのどを鳴らす「ゴロゴロ音」は、リラックスの代表的なサインです。
リラックスしているときや甘えたいとき、心地よく眠っているときなどに聞かれます。
研究によると、この「ゴロゴロ音」は猫自身の体を癒す効果もあるといわれています。骨の回復を早める周波数と似ているそうです。
お腹を見せる
猫がお腹を見せてゴロンと寝転ぶのは「信頼と安心」のサインです。猫にとってお腹は急所なので、安心できる場所でしか見せません。
ただし「お腹を見せたから触っていい」というわけではありません。中にはお腹を触られるのを嫌がる猫もいて、油断すると猫パンチが飛んでくることもあります。
人間にたとえると「布団にくるまって無防備に寝ている」ような状態。つまり「ここは安全だからリラックスしているよ」という気持ちです。
伸びをする
猫が大きく伸びをするのもリラックスしている証拠です。寝起きに体をグーンと伸ばす姿はとても可愛らしいですよね。
猫の伸びは、筋肉を伸ばして血流をよくする役割もあります。ヨガの「猫のポーズ」もここからヒントを得たといわれています。
ゆっくりまばたきをする
猫が目を細めて、ゆっくりまばたきをするのは「安心しているよ」「信頼しているよ」というサインです。
飼い主も猫にゆっくりまばたきを返すと「アイコンタクトで通じ合う」ことができます。専門家の間では「猫のキス」と呼ばれています。人間でいえば「にっこり微笑む」ようなものであり、言葉を使わずに心が通じる瞬間です。
しっぽをゆっくり揺らす
猫のしっぽが左右にゆったり揺れているときは、リラックスしている証拠です。警戒のときの「バタバタ」とは違い、穏やかな動きになります。
ソファで一緒にテレビを見ているとき、猫のしっぽがトントンとリズムを刻むことがあります。これは「ご機嫌だよ」と伝えている仕草です。
猫が安心して暮らしているときは、ゴロゴロと鳴いたり、お腹を見せたり、伸びをしたりと、わかりやすいリラックスのサインを見せてくれます。こうした行動を理解すると、飼い主も「うちの子は幸せに過ごしている」と安心することができます。
猫の「遊びたい」気持ちを示す行動

猫はもともと狩りをする動物なので、「遊び」は生きるための本能と深く関わっています。遊ぶことで運動不足を解消し、ストレスを発散し、飼い主との絆も深まります。ここでは、猫が遊びたいときに見せる行動を紹介します。
おもちゃを持ってくる
犬のように「ボールを持ってくる」ことは猫には珍しいですが、遊ぶのが好きな子はお気に入りのおもちゃを飼い主の前にポンと置くことがあります。
夜になるとネズミのおもちゃをベッドまで運んでくる猫ちゃんもいます。飼い主が寝ていてもお構いなしで「遊ぼう!」と誘っています。
これは「狩りごっこ」の一種で、獲物を捕まえたつもりで見せている行動とも考えられます。
瞳孔が大きくなる
猫は興奮すると目の瞳孔が大きく開きます。特に遊びたいときや、何かに夢中になっているときに「まん丸の目」になります。人間でいうと「スポーツ前にアドレナリンが出て目が輝く」ような状態となります。
ただし怒っているときも瞳孔が大きくなるので、しっぽや耳の動きと合わせて判断することが大切です。
かくれんぼをする
家具の影やカーテンの裏から突然飛び出すのも「遊びたい!」のサインです。狩りの本能を遊びに置きかえている行動です。
物陰から「バッ」と飛び出してきて、再び隠れたりする行動は「奇襲型の狩猟本能」で、猫の得意分野となります。こういうときは遊びに付き合ってあげると猫ちゃんは大喜びします。
しっぽをピンと立てて走り回る
家の中を全力疾走する「猫の運動会」は、遊びたい気持ちの爆発です。特に夜に多い行動で、飼い主を困らせることもあります。
猫は野生時代、夜行性の生活をしていました。その名残で夜にテンションが上がり、急に走り回ることがあります。寝る前にしっかり遊んであげると、夜中の大運動会を減らすことができます。
前足でチョイチョイと触る
飼い主の手や物に前足で「チョイチョイ」と触るのも遊びたいサインです。
飼い主さんが勉強などをしているときにノートやペンをチョイチョイされると困りますが、それは「こっちにかまって!」という気持ちの表れです。まるで人間の子どもが「遊んでよ!」と袖を引っ張るような行動です。
猫が遊びたいときは、瞳孔が大きくなったり、かくれんぼをしたり、家中を走り回ったりと、とてもエネルギッシュです。これらの行動はただの「いたずら」ではなく、本能的な「狩りごっこ」です。しっかり遊びに付き合ってあげることで、猫は健康的にストレスを解消できます。
猫が不安やストレスを感じているときの行動

猫は環境の変化に敏感で、ちょっとしたことでもストレスを感じてしまいます。
引っ越し、新しい家族の登場、大きな物音、飼い主の不在など…。
そんなとき、猫は体や行動を通じて「不安だよ」「落ち着かないよ」とサインを出しています。
ここでは、そのサインを具体的に解説します。
隠れて出てこない
不安を感じた猫は、まず安全な場所に身を隠します。ベッドの下や押し入れ、家具のすき間など、人の手が届きにくいところに潜り込みます。
野生の猫は危険を感じると巣穴に隠れます。隠れるのは「自己防衛本能」の一つで、異常ではありません。
毛づくろいが増える(過剰グルーミング)
不安なときに毛づくろいをするのは、猫にとって「気持ちを落ち着けるための行動」です。
しかし、度が過ぎて毛が薄くなるほどグルーミングする場合はストレスが強いサインです。
皮膚病と見分けがつきにくいため、気になる場合は動物病院に相談しましょう。
攻撃的になる
普段おとなしい猫でも、強いストレスを感じると急に噛んだり引っかいたりすることがあります。
新しい猫を迎えた家庭で、先住猫が突然「シャーッ!」と威嚇するようになったケースがあります。これはテリトリーが脅かされて不安になっているためです。
猫の攻撃性は「恐怖心」から出るものが多いです。無理に触らず、落ち着ける環境を作ることが大切です。
食欲が落ちる
ストレスを感じるとご飯を食べなくなる猫もいます。
特に環境が変わったときに起こりやすく、数日続くと体力低下につながります。
猫は2日以上食べないと「脂肪肝」という危険な病気を発症することがあります。お気に入りのおやつを与える、静かな環境でご飯をあげるなど工夫しましょう。
トイレの失敗が増える
トイレがきれいでも粗相をする場合は、ストレスが原因のことがあります。
不安や不満を「行動」で伝えようとしているのです。人間でいえば、ストレスで夜眠れなくなったり、お腹が痛くなったりするのと同じです。
猫はストレスを感じると「隠れる」「毛づくろいが増える」「攻撃的になる」「食欲が落ちる」「粗相をする」などの行動を見せます。
これらは「困った行動」ではなく「SOSのサイン」です。
飼い主が気づいてあげることが、猫ちゃんの安心につながります。
猫ちゃんと信頼関係を築くために大切なこと

猫ちゃんとの暮らしで大切なのは、「信頼関係をどう作るか」です。
犬のように「主従関係」を求める動物ではなく、猫は「対等なパートナー」であることを望んでいます。そのため、無理に従わせようとするのではなく、「猫ちゃんが安心して甘えられる環境を作ること」が何より大事です。
ここでは、猫ちゃんと信頼を育てるために知っておきたい行動のポイントや注意点を紹介します。
無理に触らない
猫は気分屋な一面があります。撫でられたいときには自分から近寄ってきますが、気分でないときに無理に抱っこされたり触られたりすると、不快な思いをします。
猫ちゃんが近づいてきたときに軽く撫でてあげる。逆に離れたときには追いかけずに放っておくという距離感がちょうど良いぐらいです。
ごはんや水を清潔に保つ
猫ちゃんにとって「食事を用意してくれる人」はとても大切な存在です。
ごはんや水がいつも清潔であれば、猫ちゃんは安心してその人を信頼するようになります。毎日同じ時間にごはんをあげていると、時間になると猫ちゃんは「そろそろでしょ?」という顔で待つようになったりします。
猫はきれい好きなので、水が古いと飲まないことがあります。こまめに入れ替えることが信頼につながります。
安心できる居場所を用意する
猫ちゃんは「自分だけの隠れ家」があると安心します。その場所は段ボール、キャットタワーのボックス、押し入れの一角など、猫ちゃんによって様々です。
人間にとっての来客でにぎ「自分の部屋」のようなものなので、部屋が賑やかなときに、猫ちゃんはすっーっと自分の隠れ場所に移動して、落ち着いた頃に出てきたりします。
スキンシップの質を大切にする
信頼を築くには猫ちゃんの「触れ方」が大事です。
一般的には、あごの下、首まわりをなでると喜ばれます。逆にしっぽ、足先、お腹に触れると嫌がられます。なでているときに「ゴロゴロ音」や「目を細める」などの反応を確認して、猫ちゃんの喜ぶポイントを探してみてください。
猫のサインを見逃さない
猫は「嫌だな」「うれしいな」を言葉では伝えられません。しっぽや耳、目の動きで気持ちを表現します。
例えば、しっぽをブンブン振るのはイライラしているとき、耳が横に寝ているのは警戒しているとき、ゆっくりまばたきをするのは安心しているときなどです。
こうしたサインを理解してあげることで、猫ちゃんは「わかってくれる人」と感じ、さらに信頼を寄せてくれます。
猫ちゃんと信頼関係を築くには、「無理に触らない」「食事を清潔に保つ」「安心できる居場所を作る」「やさしいスキンシップ」「猫のサインを理解する」ことがポイントです。
これを続けていけば、猫ちゃんは飼い主さんを「安心できるパートナー」と認識し、甘えてくれるようになります。
猫のしぐさからわかる健康チェック

猫は体調が悪くても、野生の名残から「弱っていることを隠す」習性があります。
そのため、飼い主が普段の様子と比べて「少し違うな」と気づくことが、とても大切です。
ここでは、健康チェックのポイントを「しぐさ」や「行動の変化」から解説します。
ごはんや水の飲み方の変化
- 食欲がない → 病気のサインかも。特に1日以上まったく食べないのは危険。
- 急にたくさん水を飲むようになった → 腎臓の病気や糖尿病の可能性がある。
猫は本来あまり水を飲まない動物です。だからこそ「急に増えた・減った」は重要なサインになります。
トイレの様子を観察する
- おしっこの回数が増えた/減った → 膀胱炎や腎臓のトラブルの可能性。
- 便がゆるい・出ていない → 消化器の異常や便秘。
いつもトイレをすぐに終える猫が、何度もトイレに行ってはしゃがむだけ…という様子が続いたので病院に行ったら、尿路結石が見つかったという例もあります。普段と違う場合は少し注意して観察してください。
歩き方や動き方の異変
- よろける・足を引きずる → 足や腰のケガ、関節の問題。
- 急に動かなくなった → 強い痛みや体調不良。
猫は人間と比べると早いスピードで歳を重ねていきます。高齢猫は関節炎になることが多く、段差を避けるようになることがあります。
毛づくろいの変化
- 毛づくろいをしなくなる → 体調が悪い、元気がないサイン。
- 逆にしすぎてハゲてしまう → ストレスや皮膚の病気。
これらは人間でいうと「身だしなみに気を使う余裕がない」状態と似ています。
鳴き声や表情の違い
- 鳴き声が変わる → 痛みや不安を訴えている場合がある。
- 表情が険しい → 不快感やストレス。
普段は静かな猫が夜中に大声で鳴き続けるようになり、検査をしたら甲状腺の病気が見つかったという例もあります。
猫の健康チェックは「普段との違い」を見逃さないことがポイントです。
食事・水・トイレ・動き・毛づくろい・鳴き声など、毎日のちょっとした変化が病気の早期発見につながります。
猫と長く幸せに暮らすために

猫の寿命は昔に比べて大きく延び、今では 15歳以上 生きる猫ちゃんも珍しくありません。
長く一緒に暮らすためには「健康管理」「安心できる環境」「飼い主の心構え」がとても大切です。
この章では、猫と幸せに暮らすための具体的な工夫を紹介します。
生活習慣を整える
規則正しい食事
- 猫にとって食事のリズムは安心につながります。
- ごはんの時間がバラバラだと、猫がストレスを感じやすいです。
野生の猫は「小分けに何度も獲物を食べる」習性があるので、1日数回に分けてあげると自然に近い食生活となります。ケースバイケースで考えてみてください。
運動を取り入れる
- 室内猫は運動不足になりやすいので、遊びの時間を意識的に作りましょう。
- おもちゃで追いかけっこをしたり、高低差のあるキャットタワーを用意すると効果的です。
心のケアも忘れずに
スキンシップの大切さ
- 猫は自由気ままに見えても、実は飼い主との触れ合いを求めています。
- 撫でる、声をかけるなど、毎日のコミュニケーションが信頼関係を深めます。
人間も「会話がなくても同じ空間にいるだけで安心」することがありますよね。猫もそれに似ています。
ストレスを減らす工夫
- 騒音や急な環境の変化は猫にとって大きなストレスになります。
- 引っ越しや模様替えのときは、安心できる隠れ場所を作ってあげましょう。
健康寿命をのばす工夫
定期健診を受ける
- 病気は早期発見が大切。年1回の健康診断が理想です。
- 高齢猫(10歳以上)は年2回が安心。
食生活の見直し
- 年齢に合わせてフードを変えることも重要。
- 高齢猫には腎臓にやさしい食事や消化のよいフードが推奨されます。
「人間でいうと1年で4歳分くらい年をとる」といわれています。
つまり、1年に1度の健診は、人間でいうと4年に1度の健康診断に近いのです。
飼い主の心構え
- 猫は一緒にいる時間が長くなるほど、家族の一員として大きな存在になります。
- 最期までしっかりお世話をする覚悟を持つことが、猫にとって一番の幸せです。
猫ちゃんを大切にすることは、自分自身を豊かにすることでもあります。
まとめ

猫と長く幸せに暮らすためには、
- 規則正しい生活習慣
- ストレスの少ない環境
- 健康チェックと定期健診
- 飼い主の覚悟と愛情
これらが大切です。
猫との日々は、特別な時間の積み重ねです。毎日の小さな工夫が、猫の寿命を延ばし、飼い主との絆を深めていきます。